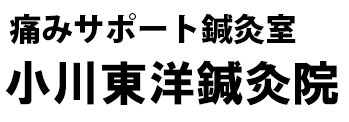大事な財産として保存しているその当時の剖検記録の写しを、今でも時々読み返すことがあります。
前記のような方法論と視点で病気を診てきた人間が、非常に素朴な鍼灸医学などという世界で生きることになった時、自分にとって病理学という存在はどんなものであったのかを改めて考えてみたことがあります。すると病理学という世界で学ぶことが出来た有難さと、現在のような将来を意図して進んだ訳ではなかったからこそ尚、病理学という世界に進めた幸運を実感し直すことが出来たのです。
なぜか?と云えば、病理学は人間の病気というものの成り立ちを明らかにすることを目的とした学問ですから、病気というものを全て対象にします。そのため、殆ど全ての診療科の病気を診ることになり、事実、病理学教室在籍中の10年間で殆どの科の患者様に向き合うことが出来ましたし、その病態を診ることが出来ました。
そのため広範な病気の知見が得られたことと、そのことで病気に対する対応の幅が広がり、そのことが現在の私にとっての強みであり、最大無二の武器となったのです。
ただ、そういう姿勢が出来上がってしまってから鍼灸師という資格を得るための教育機関に進んだためか、そこで受けた授業の東洋医学概論やら経穴学など等の東洋医学的科目の内容は、右から入っては直ぐに左から出ていくといった具合で、とうとう殆んど何も身に付きませんでした。(苦笑)
ですから今でも患者様を診る意識は西洋医学的視点であり、治療手段の鍼はあくまでも道具として使っているに過ぎません。ホームページ・タイトルの「鍼灸師もどきの鍼灸師」は自虐的な表現ではなく「実感」です。
そんな治療スタイルで三十数年、鍼灸師もどきの異端児として存在してきました。 そんな異端児の履歴を正直に書いたつもりです。